外国人雇用で知っておきたい「JLPT」と「CEFR」とは?【行政書士×日本語教師が解説】
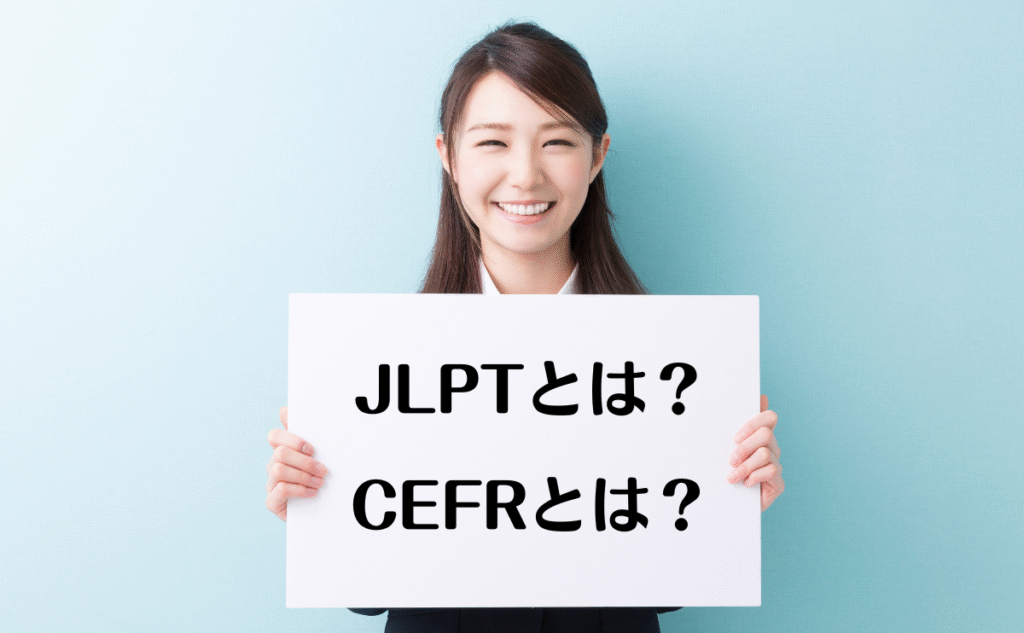
外国人従業員の方々と共に働く中で、このように感じた経験はありませんか?
- 「一生懸命説明したつもりなのに、指示がうまく伝わっていない気がする…」
- 「日常会話は問題なさそうだけど、業務に必要な日本語レベルはどのくらいなのだろう?」
- 「採用時に日本語能力をどう評価すればいいか、基準がわかりにくい」
- 「どのくらいの日本語力があれば、安心してこの業務を任せられるだろうか?」
グローバル化が進み、多くの企業で外国人材の活躍が不可欠となる中、こうしたコミュニケーションや能力評価に関する悩みは、決して少なくないのではないでしょうか。
言葉の壁や文化の違いを乗り越え、外国人従業員の方々が持つ能力を最大限に発揮してもらうためには、まず従業員の日本語能力を客観的に理解することが非常に重要です。これにより、採用時のミスマッチを防ぎ、入社後の適切な配置や効果的な育成計画、そして円滑なコミュニケーションへと繋げていくことができます。
そこで、今回の記事では、外国人従業員の日本語能力を測るための代表的な指標である「JLPT(日本語能力試験)」と「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」について、分かりやすく解説します。
この記事をお読みいただくことで、
- JLPTとCEFRがそれぞれどのようなものか
- 両者の違いやレベルの目安
- 企業としてこれらの指標をどのように採用活動や人材育成、職場環境づくりに活かせるか
といった点をご理解いただけます。
当事務所は、入管業務に携わる行政書士、そして日本語教育に携わる日本語教師としての両方の視点から、企業様が外国人材と共に成長していくためのお手伝いができればと考えております。ぜひ、貴社の外国人雇用や従業員サポートのヒントとして、本記事をお役立てください。
もくじ
JLPT(日本語能力試験)とは?
外国人の日本語能力を示す指標として、まず多くの場面で耳にするのが「JLPT(日本語能力試験:Japanese-Language Proficiency Test)」ではないでしょうか。
JLPTは、日本語を母語としない人々の日本語能力を測定し、認定することを目的とした試験です。日本では国際交流基金と日本国際教育支援協会が、海外では国際交流基金が各地の機関と協力して実施しており、世界で最も広く認知され、受験者数も多い日本語の試験と言えます。そのため、国内外で日本語能力の客観的な証明として広く活用されています。
レベルはN1からN5までの5段階
JLPTには、N1、N2、N3、N4、N5という5つのレベルがあります。N1が最も難易度が高く、N5が入門レベルとなります。それぞれのレベルで、どの程度の日本語能力が認定されるのか、大まかな目安を見てみましょう。
- N5:「基本的な日本語」をある程度理解できる
- ひらがなやカタカナ、基本的な漢字で書かれた定型的な語句や短い文を読んで理解できます。
- 挨拶や簡単な自己紹介など、ゆっくり話されれば短い会話の内容が聞き取れます。
- イメージ:簡単な挨拶や、ごく基本的な指示の理解
- N4:「基本的な日本語」を理解できる
- 身近な話題について書かれた、基本的な語彙や漢字を用いた文章を読んで理解できます。
- 日常的な場面で、ゆっくり話される会話であれば、内容をほぼ理解できます。
- イメージ:簡単な業務指示の理解、身の回りのことについて簡単な質疑応答
- N3:「日常的な場面で使われる日本語」をある程度理解できる
- 日常的な話題に関する具体的な内容の文章を読んで理解できます。新聞の見出しなどから情報の概要をつかむこともできます。
- 日常的な場面で、やや自然に近いスピードの会話を聞いて、話の具体的な内容や登場人物の関係をほぼ理解できます。
- イメージ:職場での日常的なコミュニケーション、ある程度まとまった指示の理解
- N2:「日常的な場面で使われる日本語」に加え、「より幅広い場面で使われる日本語」をある程度理解できる
- 新聞や雑誌の記事・解説など、幅広い話題について書かれたわかりやすい文章を読んで、内容を理解できます。
- 自然に近いスピードのまとまった会話やニュースなどを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係などを理解できます。
- イメージ:社内会議の内容理解、比較的複雑な業務指示の理解、同僚との一般的な議論
- ※多くの企業で、一定の業務遂行能力を期待するレベルとして目標とされることがあります。
- N1:「幅広い場面で使われる日本語」を理解できる
- 複雑で抽象度の高い文章(新聞の論説、評論など)を読んで、文章の構成や内容を理解できます。
- 自然なスピードで、まとまりのある会話、ニュース、講義などを聞いて、話の流れや内容、論理構成などを詳細に理解できます。
- イメージ:専門的な議論への参加、高度な交渉、社内外向けの文書作成のサポートなど
企業におけるJLPTの活用
このJLPTのレベルは、企業において以下のような場面で活用されています。
- 採用基準として: 募集する職種やポジションに求められる日本語レベルの目安として、「N2以上必須」「N3程度の日本語能力がある方」といった形で基準を設けている企業が多くあります。認知度が高いため、応募者にとっても分かりやすい基準となります。
- 社内教育の目標設定: 外国人従業員向けの日本語研修を実施する際に、レベル分けの基準としたり、学習の到達目標として設定したりするのに役立ちます。
- 昇進・昇格の参考指標: 職務内容によっては、昇進や昇格の際に一定レベル以上の日本語能力を求められるケースもあり、その客観的な指標としてJLPTの結果が参考にされることがあります。
このように、JLPTは外国人従業員の日本語能力を測るための、非常にポピュラーでわかりやすい指標です。まずはこのJLPTのレベル感を理解しておくことが、外国人雇用を考える上で第一歩となるでしょう。
※各レベルの目安は、JLPT公式サイトの情報を基に、より分かりやすく表現したものです。詳細については公式サイトもご参照ください。
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)とは?
JLPTと並んで、近年注目されている日本語能力の指標が「CEFR(セファール:Common European Framework of Reference for Languages)」です。日本語では「ヨーロッパ言語共通参照枠」と訳されます。
これは、もともと欧州評議会が、ヨーロッパ域内での人々の移動や相互理解を促すために開発したもので、言語の熟達度を「その言語を使って具体的に何ができるか」という実践的な能力(Can-do)で示すことを目的とした国際的な基準です。英語やフランス語だけでなく、現在では日本語を含む多くの言語の学習、教授、評価の場面で世界的に活用されています。
CEFRの最大の特徴:「Can-do(~できる)」でレベルを示す
CEFRがJLPTと大きく異なるのは、単に言語知識の量や読解・聴解の正確さだけでなく、「聞く」「読む」「話す(やり取り)」「話す(発表)」「書く」といった言語を使う活動(4技能5領域)において、具体的にどのようなことができるかという観点からレベルを設定している点です。
レベルはA1からC2までの6段階
CEFRでは、言語能力を大きく3段階、細かく6つのレベルに分類しています。下からA1、A2(基礎段階の言語使用者)、B1、B2(自立した言語使用者)、C1、C2(熟達した言語使用者)となり、A1が最も易しく、C2が最も熟達したレベルを示します。
それぞれのレベルで「何ができるか」の目安を見てみましょう。
- A1 (入門):
- 簡単な挨拶や自己紹介ができる。
- 相手がゆっくり、はっきり話してくれれば、簡単な質問に答えたり、お願いをしたりできる。
- イメージ:ごく基本的な定型表現を使ったコミュニケーション
- A2 (初級):
- 自分のことや家族、買い物、仕事など、身近で基本的な情報について簡単なやりとりができる。
- 短く簡単なメモやメッセージを理解できる。
- イメージ:簡単な日常会話、必要最低限の情報交換
- B1 (中級):
- 仕事、学校、趣味など、身近な話題について、標準的な話し方であれば主要な点を理解できる。
- 身近な話題や個人的に関心のあることについて、簡単な言葉で自分の意見や経験を述べることができる。
- イメージ:職場での慣れた話題に関するコミュニケーション、簡単な報告や連絡
- ※このレベルあたりから、多くの定型的な業務への対応が期待できるようになります。
- B2 (中級の上):
- 自分の専門分野の技術的な議論も含め、複雑な文章の主要な内容を理解できる。
- ネイティブスピーカーと、お互いに大きなストレスなく、ある程度流暢かつ自然にやりとりができる。
- 幅広い話題について、明確で詳細な文章を作成できる。
- イメージ:社内外の関係者とのある程度複雑なやり取り、会議での意見交換、報告書の作成サポート
- ※自律的に業務を進める上で、一つの目安となるレベルです。
- C1 (上級):
- 様々な種類の高度な内容の長い文章を理解し、その中に含まれる意味合いも把握できる。
- 社会的、学術的、職業上の目的で、柔軟かつ効果的に言語を運用し、自分の考えを流暢かつ自然に表現できる。
- 複雑な話題について、明確で論理的な、詳細な文章を作成できる。
- イメージ:高度な交渉、プレゼンテーション、複雑な報告書・企画書の作成
- C2 (熟練):
- 聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に理解できる。
- 様々な情報源から得た情報を要約し、一貫性のある議論や説明を再構築できる。
- 非常に流暢かつ正確に、また複雑な状況でも細かいニュアンスまで区別しながら自己表現ができる。
- イメージ:ネイティブスピーカーと遜色ないレベルでのあらゆるコミュニケーション
企業におけるCEFR活用の視点
CEFRのレベルは、「具体的に何ができるか」を示しているため、
- 職務内容と必要な言語能力を結びつけやすい: 「この業務には、最低でもB1レベルの『話す(やり取り)』能力が必要だ」といった形で、より具体的に求めるスキルを定義するのに役立ちます。
- 実践的なコミュニケーション能力の把握: 特に「話す」「書く」といったアウトプット能力を含めて評価する視点は、実際の業務におけるコミュニケーション能力を推測する上で参考になります。
- 研修目標の具体化: 「次のステップとして、B1レベルのCan-do記述にある『〇〇ができる』ようになることを目指そう」といった形で、具体的な学習目標を設定しやすくなります。
JLPTとCEFRは、どちらが良い・悪いというものではなく、それぞれ特徴があります。次の章では、この二つの指標の関係性や使い分けについて見ていきましょう。
JLPTとCEFRの関係性と使い分け~二つの指標をどう活かすか?
ここまで、日本語能力を測る代表的な指標として「JLPT」と「CEFR」をそれぞれご紹介してきました。では、この二つの指標にはどのような関係があり、企業としてはどのように使い分けていけばいいのでしょうか。
レベル対応の目安
まず、気になるのが「JLPTのN〇は、CEFRだとどのくらいのレベルなの?」という点だと思います。国際交流基金などの機関が、両者のレベルについて以下のような対照関係(目安)を示しています。
| JLPT レベル | CEFR レベル (目安) |
| N1 | B2 ~ C1 |
| N2 | B1 |
| N3 | A2 ~ B1 |
| N4 | A2 |
| N5 | A1 |
ただし、これはあくまで大まかな目安です。 なぜなら、JLPTとCEFRでは、測定している能力の側面が異なるからです。例えば、JLPTは「読む力」「聞く力」の比重が大きい一方、CEFRは「話す力」「書く力」も含めた実践的な運用能力を評価する枠組みです。そのため、「JLPT N2に合格しているけれど、CEFRのB1レベルで求められる『話す力』はまだ少し苦手」といったケースも十分にあり得ます。この違いを理解しておくことが重要です。
JLPTとCEFRの主な違いをおさらい
両者の特徴を改めて比較してみましょう。
| 特徴 | JLPT (日本語能力試験) | CEFR (ヨーロッパ言語共通参照枠) |
| 主な測定能力 | ・読む力 (読解) ・聞く力 (聴解) ・言語知識 (文字・語彙・文法) | ・聞く ・読む ・話す(やり取り) ・話す(発表) ・書く (4技能5領域) |
| 評価の視点 | 日本語の知識や理解度 | その言語を使って「何ができるか」 (Can-do) |
| 形式 | マークシート方式の客観テスト (試験そのもの) | 言語能力記述の枠組み (フレームワーク) |
| レベル表示 | N1~N5 の5段階 | A1~C2 の6段階 |
| その他 | ・客観的なスコア ・合否判定 ・認知度が高く比較しやすい | ・実践的な運用能力の把握 ・具体的な学習目標の設定 ・多言語で共通の基準 |
企業における使い分け・併用のヒント
これらの特徴を踏まえ、企業では以下のように使い分けたり、組み合わせて活用したりすることが考えられます。
- 《採用選考の場面で》
- 書類選考・一次スクリーニング: 多くの応募者の中から、業務に必要な最低限の日本語理解力(読解・聴解)を持つ人材を効率的に見つけるためには、認知度が高く客観的なレベルが示されるJLPTの基準(例:「N2以上」)を活用するのが有効です。
- 面接: 書類選考を通過した候補者に対して、より実践的なコミュニケーション能力を確認するために、CEFRのCan-doリストを参考に質問を設計します。例えば、「B1レベル」を想定し、「〇〇(具体的な業務場面)について、あなたの意見を説明してください」「△△(過去の経験)について、簡単に報告してもらえますか?」といった質問を通して、「話す力」や状況に応じた対応力を見極めます。
- 《入社後の育成・研修の場面で》
- 現状レベルの把握: JLPTの結果は、従業員の日本語の基礎知識や理解度の大まかな目安として役立ちます。
- 具体的な目標設定と研修計画: CEFRのCan-do記述を活用し、「次はB1レベルの『簡単な報告書を書ける』ようになることを目指そう」といった具体的な行動目標を設定します。そして、その目標達成に必要なスキル(語彙、文法、表現、会話練習、作文練習など)を盛り込んだ研修プログラムを計画・実施します。CEFRは学習者が「できるようになること」を意識しやすいため、モチベーション維持にも繋がります。
- 《人材配置・業務分担の場面で》
- JLPTレベルで基礎的な日本語理解力を考慮しつつ、CEFRの視点(特に「話す」「書く」能力や、どのレベルの「やり取り」が可能か)も加味して、担当業務のコミュニケーション要件(顧客対応の有無、会議での発言頻度、作成する文書の種類など)と照らし合わせ、より適切な配置や業務分担を検討します。
このように、JLPTとCEFRはそれぞれに異なる強みを持つ指標です。どちらか一方だけが優れているというわけではありません。両方の特徴を理解し、企業の目的や場面に応じてうまく使い分けたり、組み合わせて活用したりすることで、外国人従業員の日本語能力をより多角的に、そして的確に把握し、採用や育成、そして円滑なコミュニケーションへと繋げていくことができるでしょう。
企業が日本語能力指標を活用するメリット
これまでJLPTとCEFRという二つの日本語能力指標について見てきましたが、これらの指標をただ知っているだけでなく、企業活動の中で積極的に「活用」することには、多くの具体的なメリットがあります。外国人従業員の採用から育成、そして定着に至るまで、様々な場面で役立ちます。
メリット1:採用時のミスマッチを減らし、的確な人材確保へ
募集する職務に「どの程度の日本語能力が必要か」を、JLPTやCEFRのレベルなどを基に具体的に定義し、募集要項に明記することで、応募者との間で期待値のズレを防ぐことができます。面接での主観的な印象だけでなく、客観的な指標を用いることで、より自社の求める能力に合った人材を選考しやすくなります。結果として、「思ったより日本語でのコミュニケーションが難しい」「業務指示の理解に時間がかかる」といった入社後のミスマッチを減らし、早期の活躍を期待できる人材の確保に繋がります。
メリット2:適切な人材配置と円滑な業務コミュニケーション
従業員の日本語能力、特にCEFRが示す「話す」「書く」といった実践的な能力レベルを把握することで、その能力を最大限に活かせる部署や業務に配置することが可能になります。例えば、顧客対応が多い部署にはB2レベル以上のコミュニケーション能力を持つ人材を、定型的な業務が中心であればB1レベルの人材を、といった判断がしやすくなります。また、相手のレベルに合わせて業務指示の言葉遣いや説明の具体性を調整できるため、指示内容が正確に伝わり、認識の齟齬によるミスや手戻りを減らすことができます。
メリット3:効果的・効率的な日本語教育計画の実現
「どのレベルの日本語能力を、いつまでに習得してほしいのか」という目標設定が、JLPTやCEFRのレベルを用いることで具体的に行えます。従業員の現在のレベルを客観的に把握し、目標レベルとのギャップを明確にすることで、一人ひとりに合った効果的な研修計画(使用教材、学習内容、期間など)を立てることが可能になります。画一的な研修ではなく、レベルに応じたきめ細やかな教育を提供することで、効率的なスキルアップを支援できます。
メリット4:従業員の学習モチベーション向上とエンゲージメント強化
「JLPTのN2合格を目指す」「CEFRのB1レベルのCan-doを達成する」といった明確な目標は、従業員自身の日本語学習への意欲を高める大きな動機付けとなります。企業が日本語能力の向上を評価し、学習機会の提供や資格取得支援などのサポートを行う姿勢を示すことは、従業員の会社への貢献意欲やエンゲージメント(愛着や信頼感)を高めることにも繋がります。能力向上が昇進・昇格、手当、担当業務の拡大などに結びつく制度があれば、さらに効果的でしょう。
メリット5:在留資格手続きにおけるプラス要素となる可能性(行政書士視点より)
これは特に私たち行政書士の視点からですが、特定の在留資格(例えば「特定技能」など)においては、日本語能力が許可要件の一つとなっています。JLPTなどの公的な試験の合格証明書は、その日本語能力を客観的に証明する有効な資料として広く認められています。在留資格の新規申請や更新手続きにおいて、求められる日本語能力を明確な形で示すことができると、審査がスムーズに進んだり、総合的な判断において有利に働く可能性があります。(※もちろん、日本語能力だけで許可が決まるわけではなく、他の要件も重要です。最終的な判断は入国管理局によります。)
このように、日本語能力指標を理解し活用することは、外国人従業員の採用、育成、配置、そして定着といった人事戦略全体において、企業に多くのメリットをもたらします。ぜひ、これらの指標を有効活用し、外国人従業員がいきいきと活躍できる職場環境づくりにお役立てください。
当事務所ならではのサポート体制
ここまで、JLPTとCEFRという日本語能力指標の概要や活用メリットについて解説してきました。これらの知識を踏まえた上で、外国人従業員の採用、育成、そして定着を成功させるためには、専門家によるサポートが有効な場合があります。
当事務所は、入管業務を専門とする行政書士であると同時に、日本語教育の現場経験を持つ日本語教師でもあります。この二つの専門性を掛け合わせることで、他にはない独自の視点から、外国人雇用に取り組む企業様を力強くサポートできるのが最大の強みです。
【強み①】行政書士として:在留資格(ビザ)のエキスパート
外国人の方を雇用する上で避けて通れないのが、在留資格(ビザ)の問題です。「どのような在留資格が必要か」「申請・更新手続きはどうすればよいか」「この業務内容ならどの資格に該当するのか」など、複雑で分かりにくい点も多いかと思います。 当事務所では、入管法や関連法規に関する専門知識に基づき、
- 適切な在留資格の選択に関するアドバイス
- 各種申請書類の作成・提出代行
- 在留資格と日本語能力要件の関係性に関するコンサルティング
- コンプライアンス(法令遵守)に関する助言
など、企業の状況に合わせた的確なサポートを提供します。特に、在留資格申請において日本語能力をどのように証明すれば審査上有利になるか、といった実践的なアドバイスも可能です。
【強み②】日本語教師として:実践的な日本語教育サポート
「従業員の日本語レベルを客観的に把握したい」「レベルに合った効果的な学習方法を知りたい」「JLPTや特定技能の試験対策をどう進めればよいかわからない」といった日本語教育に関するお悩みにも対応いたします。 日本語教師としての知識と経験を活かし、
- 従業員の日本語レベルチェック(JLPT・CEFRの目安判定含む)と課題分析
- レベルや目標に応じた学習プランの提案、教材選定のアドバイス
- JLPTや特定技能評価試験などの試験対策に関する具体的な指導・相談
- 企業内での日本語研修プログラムの企画・改善に関するコンサルティング
など、単なるレベル判定に留まらない、実践的なサポートを提供します。従業員の方々の「できる!」を増やし、自信を持って業務に取り組めるよう支援します。
「行政書士 × 日本語教師」だからできる、一貫したサポート
この二つの専門性を組み合わせることで、例えば、
- 在留資格の更新時期を見据え、計画的に必要な日本語レベル達成を支援する
- 「特定技能」への在留資格変更を目指す従業員に対し、試験対策から申請手続きまでワンストップでサポートする
- 日本語能力が原因で業務上の課題がある場合、そのレベルを把握し、適切な研修を提案しつつ、必要であれば在留資格上の留意点もアドバイスする
といった、多角的で一貫性のあるサポートが可能になります。「ビザのことも、日本語教育のことも、まとめて相談したい」という企業様のニーズに的確にお応えできるのが、当事務所ならではの価値です。
継続的なサポート:サブスクリプション(顧問)サービスのご案内
こうした専門的なサポートを、必要な時に、継続的に、そして気軽に利用していただくために、当事務所ではサブスクリプション(顧問)サービスもご用意しております。 月額定額制で、
- 在留資格に関する相談・手続きサポート
- 従業員の日本語レベルや学習に関する相談
- 特定技能に関する情報提供・相談
- その他、外国人雇用に関する各種相談
などを、いつでも気軽にご利用いただけます。企業の規模やニーズに合わせてプラン内容を柔軟に調整することも可能です。一人事務所ならではのフットワークの軽さと、きめ細やかな対応で、貴社の外国人雇用に関する様々なお悩みに伴走いたします。
外国人材の活躍は、これからの企業成長の鍵となります。当事務所は、そのための土台となる「在留資格」と「日本語コミュニケーション」の両面から、専門性と親身さをもって貴社をサポートするパートナーでありたいと考えています。
まとめ
今回の記事では、外国人従業員の日本語能力を客観的に把握するための代表的な指標である「JLPT」と「CEFR」について、それぞれの特徴やレベルの目安、関係性、そして企業における具体的な活用メリットを解説してきました。
これらの指標を正しく理解し、採用活動や人材育成、日々のコミュニケーションの中で適切に活用することは、
- 採用時のミスマッチを防ぎ、
- 入社後のスムーズな業務遂行を助け、
- 効果的な日本語教育によって従業員のスキルアップを促し、
- 結果として、外国人従業員の定着と活躍に繋がります。
これは単に業務効率を高めるだけでなく、多様なバックグラウンドを持つ従業員が互いを理解し尊重し合い、共に働きがいを感じられる職場環境、すなわち「共生」を実現するための重要なステップでもあります。
外国人材の活躍が企業の持続的な成長にますます不可欠となるこれからの時代において、本記事でご紹介した内容が、貴社にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
まずはお気軽にご相談ください
「外国人従業員の日本語レベルについて、もっと具体的に相談したい」 「在留資格の手続きと合わせて、日本語教育についてもアドバイスが欲しい」 「特定技能制度の活用や、関連する試験対策について詳しく知りたい」 「自社に合ったサポート内容や、サブスクリプションサービスについて聞いてみたい」
もし、このような課題やお考えをお持ちでしたら、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は、入管業務の専門家である行政書士、そして日本語教育の専門家である日本語教師、この二つの視点を併せ持つことを強みとしています。貴社の状況やニーズを丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。
▼個別のご相談・お問い合わせはこちらから
初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
▼継続的なサポートにご興味のある方はこちら

貴社からのご連絡を、心よりお待ちしております。

